【最近読んだ本なんてない!】就活面接での「最近読んだ本」の“答え方”教えます。
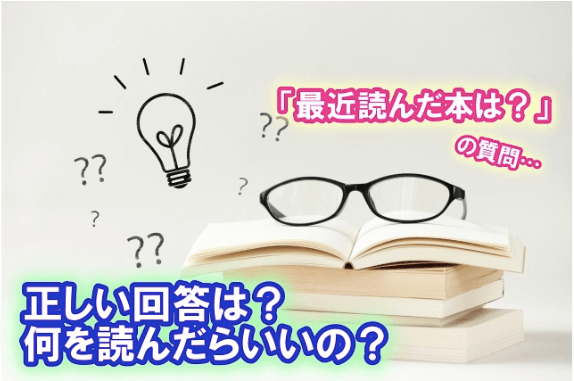
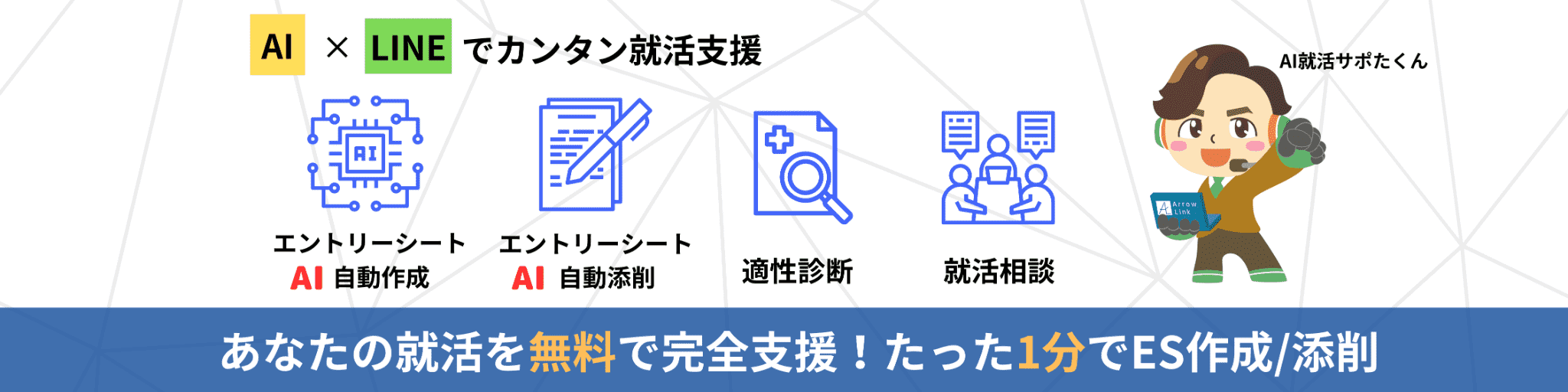
「最近読んだ本は?」と、尋ねられて、あなたはすぐに答えられますか?
この記事では、普段本を読む人・読まない人、どちらの人にも役立つ面接時の応対の仕方について解説します。
そもそも、最近読んだ本を尋ねて、企業は何を知りたいのでしょうか。
そして、どのような答え方をすれば、企業に「採用したい」と、思ってもらえるのでしょう。
この記事では、「最近読んだ本は?」の質問に対するベストな答え方と、これから読むならどんな本がいいのかについても取り上げていきます。
見たい場所へジャンプ
「最近読んだ本は?」その質問の意図とは?
面接官が「最近読んだ本は?」と、尋ねるその質問の意図は、何なのでしょうか。
アイスブレイクの一環として尋ねられることもありますが、きちんと意図があって質問されている場合もあります。
目的がはっきりすることで、どんな答え方をすればいいかが分かります。
読書週間の有無を知りたい
最近読んだ本について尋ねることで、その学生に読書習慣があるのかどうかを知るのが目的です。
読書習慣は、社会人として働くうえでとても大切な習慣です。
読書から学ぶこともできますし、普段から読書していることで周囲とのコミュニケーションの話題作りができます。
想像力も鍛えられ、相手の気持ちを考えたり、これから起こることを予測したりすることの訓練にもなります。
読書習慣は、日々積み重ねていくことで深みを増します。
ネットで検索するような情報収集では得られない、総合的な考える力が身につく習慣です。
この習慣の有無は、採用に関わる重要事項といっても良いでしょう。
学生の好み・関心について知りたい
どんな本を読んでいるか知ることで、学生たちの趣味趣向を理解できます。
本のセレクト次第でその人の性格が想像できたり、社風に合った人物かどうかも判断することができたりするでしょう。
学生の語彙や知識の量を知りたい
本の中には、理解が難しい本や、誰でも理解できるようなやさしい本など、難易度に違いがあります。
そのため、どんな本を読んでいるか知ることで、その学生の語彙力、知識量を知ることができます。
もちろん、時にはやさしい本を読むこともあるでしょう。
言葉の難しさだけが、読書の価値を決めるわけではありません。
しかし、あまりにもカジュアルな内容のものばかりを読んでいると、簡単な本しか読まない、語彙力の少ない人と思われるでしょう。
企業や仕事への貢献度を量りたい
読書を習慣にしているかどうかは、学習意欲が高いかどうかを知るのにも役立ちます。
学習意欲が高いということは、仕事に必要なことを自分自身で学べることを示します。
また、読書からヒントを得て、新商品を開発するということもあるでしょう。
企業や仕事への貢献度といってもさまざまです。
ルールを守り、業務をきっちりこなして貢献する人、新しい発想で新商品を開発する人、ものを売るのが得意な人など、さまざまな貢献度があります。
しかし、貢献をする人の傾向をみていくと、学習意欲が高く、改善・改良を自分自身で行えるタイプの人が多いです。
このタイプの人は、セミナーへ参加したり、読書をしたりと、いろいろな方法で学ぼうとします。
採用側は読書の有無を通して、その人の貢献度を知ろうとするのです。
人間性や個性について知る機会にしたい
本を選ぶ際には、その人の個性が現れます。
同じ小説でも、サスペンスなら「スリル感があるものが好き」、ファンタジーなら「想像力豊か」など、なんとなく性格のイメージが浮かぶのではないでしょうか。
また、ビジネス本などにおいては、選ぶ本は“自分に足りない”と感じている内容のものが多いでしょう。
採用側は、選ぶ本のラインナップを見て、就活生自身が何に悩んでいるのか、何を身につけようとしているのか、捉えることができます。
選ぶ本の量によっては、苦手を克服しようと頑張る人間性も見えてくるでしょう。
普段から本を読んでいる人の場合の答え方

ここからは、どんなふうに回答すればいいか迷っている方のために、回答の構成をご紹介します。
以下の構成を踏まえれば、スマートに要点の伝わる文章になります。
- 冒頭で読んだ本を提示
- その本を読んだ経験
- 本の概要・あらすじ
- 読み終えて得たことを、どう活用するか/活用している
まず、冒頭では端的に本のタイトルを言います。
そして、次のその本を手に取るにいたった経緯を説明しましょう。
次に、その本を知らない面接官のために、簡単な概要の説明をします。
あらすじの説明は、最低限でOKです。
最後に、この本を読んで得たこと、そして、それがこれから、またはすでにどんな場面で活きているかを説明しましょう。
得たことだけを説明するのではなく、その知識を利用して何ができるかまで落とし込むことが必要です。
例文を示します。
私が最近読んだ本は、○○○○さんの「○○○○」という小説です。 この本を読んだのは、ゼミの教授の推薦で、私にとても役立つだろうというので読むことにしました。 この本は、私が研究する○○○について書いてあるものです。 今まで常識だと思っていたことが覆される、驚くべき内容でした。 この本を読んだことで、私は研究の仮説を見直すことになりました。 視点を変え、多角的に物事を見ることが、新しい仮説のヒントになったのです。 常識の中で考えてばかりいても、新しいものは生まれないでしょう。 仕事では、この教訓を生かして、常に新たな視点で物事を見るようにしたいと思います。
このように、自分の言葉で説明するように心がけましょう。
普段から本を読んでいる方は、素直に最近読んだ本から一冊をチョイスしてください。
これから読もうとしている本など、読んでいない本は答えないようにしましょう。
嘘がバレれば信頼されなくなります。
本はどんな本でも構いませんが、漫画などは避けることが大切です。
小説やビジネス本、自己啓発本などから選ぶと無難です。
本を読まない人の答え方

さて、次は普段から本を読まない人の場合の答え方についてです。
「最近読んだ本」を尋ねられたら、どう答えればいいのでしょうか?
「読まない」はNG! 読んでから面接へ臨んで!
本を読まない人の場合、面接で「最近読んだ本は?」と聞かれると答えに困るかもしれません。
そこで、素直に「本は読まない」と、答える人もいるでしょう。
しかし、採用面接で本を読まないと答えるのはNGです。
「だって、本当に読んでないから……」と、いいたくなるかもしれませんが、採用面接に向けて、まずは一冊でもいいので本を読みはじめましょう。
面接を受けるまでには、最低でも3冊は読んでおくと安心です。
前述の通り、読書をすることは、ビジネスの場では必須といえる習慣です。
学ぶ向上心、コミュニケーションにおいての話題作りなど、企業が従業員に求める素質は、読書をすることで養うことができます。
だから、本を読まないと面接の場で答えてしまうのはNGです。
ビジネスをする人の素養がないと思われてしまいます。
これからビジネス社会で働くのであれば、この記事をきっかけに読書の習慣を身に着けましょう。
読まない派にもぴったり! おすすめ書籍
本を読まない人の中には、「どんな本を選べばいいのかわからない」という人も多いと思います。
そこで今回は、本を読まない派の方にもおすすめの書籍を2冊ご紹介しましょう。
まず手始めに、読んでみてはいかがでしょうか?
自分を変える習慣力/三浦将(クロスメディア・パブリッシング)
まさに、読書習慣を身に着けたいという方におすすめの一冊です。
「三日坊主になってしまう」「寝坊しがち」など、社会人になる前に直しておきたい習慣がある方も、ぜひ読んでみてください。
無理をしたり、頑張ったり、根性論で習慣を変えるのではなく、自然と習慣化していくポイントが書かれています。悪癖を正すだけでなく、一つのことを継続するのが苦手なタイプの方にも読んでいただきたい一冊です。
書籍の詳細はこちら
https://www.cm-publishing.co.jp/9784844374442/
決断力/羽生善治(角川新書)
羽生善治さんは、将棋ファンでなくとも名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。
一冊の中には、誰もが感銘を受ける名言が詰まっています。
この本のテーマは、勝負に際しての決断力です。
羽生名人も、多くの勝負を勝ち抜けてきた一人ですが、ビジネスにおいても勝負はつきものです。
ビジネスにおいても、哲学的な一冊になることは間違いないでしょう。
この本の初版は2005年と、かなり以前に出版された本です。
それが、2018年に国民栄誉賞を受賞したことで再注目を浴びることになりました。
羽生名人のトピックは、面接官にも分かりやすい内容です。
社会へ出たあとでも、話題作りに役立つので、ぜひ、読んでおきましょう。
書籍の詳細はこちら
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g200408000190/?cvid=ssuggest
読書習慣を身につけるのが最良の対策
「最近読んだ本は?」という質問に答えるには、実際に本を読むしかありません。
「本を読まずにできる方法はないの?」と、思うかもしれませんが、横着をするのはやめましょう。
読書習慣を身につければ、社会人になってからもその習慣が役立ちます。
広い知識を身につけることができ、それが仕事にも生きるはずです。
「最近読んだ本は?」という質問には、“あなたのことを知りたい”企業の思惑が含まれます。
これを機に読書習慣について改めて考え直してみてはいかがでしょうか?
弊社では、就活生の皆様のお悩み解決をできるキャリアークを提供しています。
現役の人事担当が少数人数でサポートしており、1on1での面接対策も行っているのが特徴です。
他にも、LINEで友達登録していただくと、簡単な質問に答えるだけで自己PRの自動作成や自動添削もご利用いただけます。
LINEで手軽に無料で利用できるので、就職活動にお悩みの際はぜひご利用ください。
Careearc(キャリアーク) – 日本一オモロく学べる就活道場!

